ご先祖様について
このページは、自分の姓(箱守家)の家系についての伝承や、インターネット調査で分かったことをまとめたページです。※内容には確実でないものも含まれています。
更新履歴
- 日本姓氏語源辞典で箱守(はこもり)さんの由来と分布の情報を見つけました。(2020年8月)
https://name-power.net/fn/%E7%AE%B1%E5%AE%88.html - 栃木市箱森城についての情報を見つけました。(2017年8月)
https://sayama64.blog.ss-blog.jp/2017-08-12 - 箱守城に関する情報を見つけました。(2013年8月)
http://tochichu.web.fc2.com/tochigishi4.html#hakomoro - 箱森長江氏に関するコンテンツを見つけました。(2013年4月)
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/nagae/hakomorinagaesi.html - 「タクジローの日本全国お城めぐり」で箱守姓についてのコンテンツを見つけました(2012年5月) http://castle.slowstandard.com/10kanto/15ibaragi/post_586.html
- 「名字由来net」の箱守姓が更新されました!(2012年2月16日)
http://myoji-yurai.net/searchResult.htm?myojiKanji=%E7%AE%B1%E5%AE%88 - 関城跡付近の八幡神社の情報を見つけました。(2015年12月)
https://yaokami.jp/1081574/ - ブログで記事を書きました。(2012年2月25日)
「姓氏家系大事典」(丹羽基二・著) と「姓氏家系大辞典」(太田亮・著)を国会図書館で家系について調べた
様々な説
下記に記すのはネットで声をかけさせていただき、返信をしていただいた方からの貴重な情報を掲載させていただきました。(情報を送っていただいた皆様、本当にありがとうございます。)この中からさらに「そう言えばこんな話、聞いたことがあったな」「この部分はこうだったんじゃないか」など、真相に迫る事実が判明していければ幸いです。
1.護良親王の重臣説
護良親王(もりよししんのう):
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B7%E8%89%AF%E8%A6%AA%E7%8E%8B (wikipediaより)
南北朝時代、南朝の護良親王の重臣だったという説。護良親王は主に財政面を取り締まっていた人物。
護良親王の墓を守った墓守がなまって「箱守」になったという説。
また、名前の由来を考えると、
財政面を担当 → 金庫番 → (金庫の)箱を守る → 箱守
というのも、あながち否定できない。
しかし護良親王の墓は現在鎌倉近辺にあり、茨城県に多い苗字であることの説明が若干難しい。
(H.E.さんから情報提供いただきました)
2.関城の城主、関一族のお墓を守っていた説
茨城県真壁郡関城町(現:茨城県筑西市)には関宗祐の墓が残っている。この地域で「墓」「遺跡」と言えば関宗祐の墓が非常に有名であり、墓守をするための地理性を十分に備えている。
またこのあたりには箱守姓が非常に多く密集しており、地理的にも、苗字の由来の妥当性からも、十分に納得しうる説である。
参考ページ: 関城(関城町関館:(4)に箱守についての記述あり)
大きな地図で見る
(H.D.さん他、WEBページから情報提供いただきました)
3.古河公方の家臣説
古河公方(こがくぼう):
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E6%B2%B3%E5%85%AC%E6%96%B9 (wikipediaより)
室町~戦国時代に下総国古河(茨城県古河市)を本拠とした関東足利氏。
茨城県古河市は、現在でも箱守の苗字が多く存在する茨木県真壁郡関城町(現:筑西市)とは地理的にも近く、何らかの関係があっても不思議ではない。
(H.M.さんから情報提供いただきました)
4.長沼時村の子孫説
■日本の名字7000傑
http://www.myj7000.jp-biz.net/7000/6100f.htm
6794位「箱守」を調べると、「箱森と通ず。下野発祥、藤原氏秀郷流。現在、茨城県真壁郡関城町に多い。」とある。(IEでしか閲覧できない。)
→上記から「藤原秀郷流」を辿っていくと、下のページに行き着く。
http://www.myj7000.jp-biz.net/clan/02/020/02020e2.htm
藤原秀郷の子孫に長沼時村という人物がおり、そこから筥室(はこむろ)、筥村(はこむら)、筥森(はこもり)に分かれたようである。
■箱森城(栃木市箱森町)
http://yogoazusa.my.coocan.jp/totigisi.htm#hakomori
■長沼時村の居館が栃木県にあり、別称が箱森城という。
http://marie.saiin.net/~tochigi-castle/gohen.htm
(情報提供元: WEBページ)
5.守永親王を見送った説
上記2.の流れとしての説。
関城跡の北西に大将山公園という場所があり、関城落城の際に守永親王を奥州宇津峰城にお送りする為、関城の将士が別れの宴を催したと伝えられている。
■守永親王
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E6%B4%A5%E5%B3%B0%E5%AE%AE
(H.R.さんから情報提供いただきました)
参考ページ
■関城の写真
https://kojodan.jp/castle/1308/photo/
■関城(箱守家との関連説明)
http://otakeya.in.coocan.jp/info02/taihousekikoma.htm#seki
■茨城県西地方の南北朝期の城郭
http://yaminabe36.tuzigiri.com/ibaraki_seibu/seki_taihou.htm
今後 確認したい書籍
関城町の昔ばなし ふるさと文庫
https://www.lib.pref.ibaraki.jp/licsxp-kopac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000389463
関城町の歴史
https://www.lib.pref.ibaraki.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?urlNotFlag=1
由来についての考察
誰かの墓を守っていたこと。墓守(はかもり)がなまって、もしくは何らかの理由によって(例えば南北朝時代に南朝側について衰退し、存在を隠さなければならなかった、など)箱守になったという説。この説は多数の箱守家から聞くことができ、「墓守」が変化して「箱守」になったという流れは、十中八九 間違いないと思われる。
ここで問題なのは誰の墓か、ということだ。親類縁者の絆が現代よりも数倍重要視されていたこの時代に、墓の主と何のゆかりもない人間が急に墓守を命じられるとは考えにくいし、墓の管理をするのであれば、遠距離より近距離に居住地がある方が何かと便が良いと考えるのが普通だろう。
上記4.からの流れを考えると、苗字が「箱守」になったのは「箱森」からであると考えられる。この場合の「箱森」は長沼時村という人物の子孫だが、歴史上どこかの流れで関氏との関係を持ち、「箱守」に変わったと考えられる。
家紋について
私の先祖の墓の家紋は、いわゆる「下がり藤」である。
しかし、以前 茨城県真壁郡関城町にある「箱守」姓の墓が非常に多くある墓所に行ったところ、「箱守」姓の墓にある家紋はさまざまで、「五七の桐」や 「三つ葉葵」の家紋が見られた。
ここから推測になるが、「(同じ地域で)同じ姓でも家紋が多数ある」ことが何を表しているかといえば、「発祥が異なる」ということではないだろうか。明治維新後、一般市民(農民が多数?)が苗字を持てるようになり、苗字を何にしようかという際に、土地の特徴からとったり、商売からとったり、ゆかりのある人から苗字を貰うということは普通だったようだ。そのため直系ではないが、苗字は同じでも家紋は後からつけた、ということもあり得ると考えられる。家紋が違うのはそのためではないかと考えている。
ご先祖さまを調べる理由
以前から他の人から珍しい苗字だと言われることが多かったが、きちんとした名前の由来を答えることができず、どのような由来があるのか知りたいと思っていた。
私の父の生まれは茨城県真壁郡関城町(現:茨城県筑西市)である。その近辺では箱守という姓が非常に多く、分散していないことから、同じ姓が密集していること自体が、何か特別な意味を持っているのではないかと感じていた。
現在ではインターネットが普及し、個人でも比較的容易に情報をあつめることができるようになったため、インターネットを使って自分のご先祖様のルーツをたどろうと思いに至った。
調べてみて
歴史は勝者によって作られることが多いため、敗者の側の歴史は、文献や石碑などから消され、歴史の闇に葬られることが往々にしてあり得る。 そのような貴重な文献や石碑が現存していれば検証することができるのだが・・。
Google AD
公開日:
最終更新日:2021/09/26
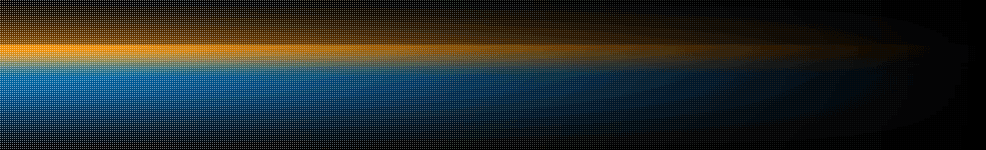





 RSS
RSS




