自分の非を認める。傍観者は気にしない。
今回のプロジェクトは、結果的にはうまく行ったとは言えませんでした。個人的には「何とかなった」という感想です。
理由は色々思いつくし、携わった人によってもあれが悪かった、これが悪かったと指摘したくなると思います。
しかし、今やるべきことは、あらさがしをして犯人を責めることではなく、うまく行かなかった事実を真摯に受け止め、次に生かすことだと思います。
「次に生かす」ということを具体的に言うと、同じことを繰り返さない。次はうまくやる。
今回は大成功だったな!と思えるように行動する。
ローソン副社長の玉塚氏がこのように言っています。
悔しくて、コンチクショウと思ったが、僕の能力が足りなかったのは事実
http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20131205/256737/?n_cid=nbpnbo_leaf_bn
あれが悪い、これが悪いと言う前に、自分にも非があったことを素直に認め、同じことを繰り返さないということ。
これがプロジェクトにとって大切なことなんだと思います。
日経ビジネスにこんな言葉も載ってました。
上司に逆らってでも自分の信念を曲げるな。失敗しても俺が骨を拾ってやる
http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20131205/256735/?rt=nocnt
新しいことにチャレンジしようとしたり、大きなことをしようとしたとき、外野にいる傍観者はかならず陰で批判します。
それは妬みであり、嫉みです。
能力のない人はチャレンジしようとしない。
現状で満足したまま、誰かが失敗したときに限って足をすくい、それ見たことかとここぞとばかりに大きな口を出す。
外野で傍観者でいることはとても楽なことです。
何にもチャレンジしなくていい。何も考えなくていい。
普段はへらへら周りに合わせて笑っていればいいだけです。
そうでないのなら、自分自身が失敗を引き受け、腹にすえ、覚悟を持って事にあたるということだと思います。
それ以前に、個人のマインドを育てる土壌は重要だと言えるでしょう。
高所から飛び降りても、下が芝生なのか、固いコンクリートかでは、飛び降りる勇気も変わってくる。
下は固いコンクリートだ。お前がどうなろうと知らんが、とにかく飛び降りろ!というのは完全にブラックと言えるでしょうね。
逆に、失敗しても骨は俺が拾ってやる、と言われれば、どんなに勇気がでることでしょう。
Google AD
- 前の記事
- 朝ウォーキングするようになった
- 次の記事
- 日経新聞取り始めた
関連記事
-
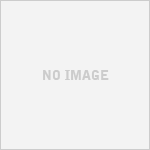
-
Hey, what a stupid guy Lahood is?
Helped. Because he is American. Americans is stupi
-

-
革命で命を落としていくものたち
昨年からGoogle Glassに興味が引かれっぱなしで、その流れでTelepathy on
-
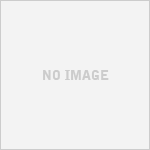
-
ソーシャルということ
「ソーシャル」という言葉がひと段落した今だからこそ。ゲームビジネスやコミュニケーションなど色
-
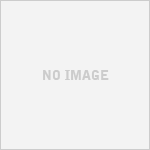
-
コミュニケーション能力について2
コミュニケーション能力について http://hakomori.net/?p=848 また人
-
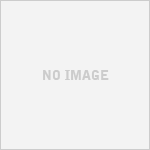
-
手段の目的化とコミュニケーション
今どんな人が求められているか、自分なりに考えてみました。すごい人を求めてるんじゃなくて、解決できる人
-
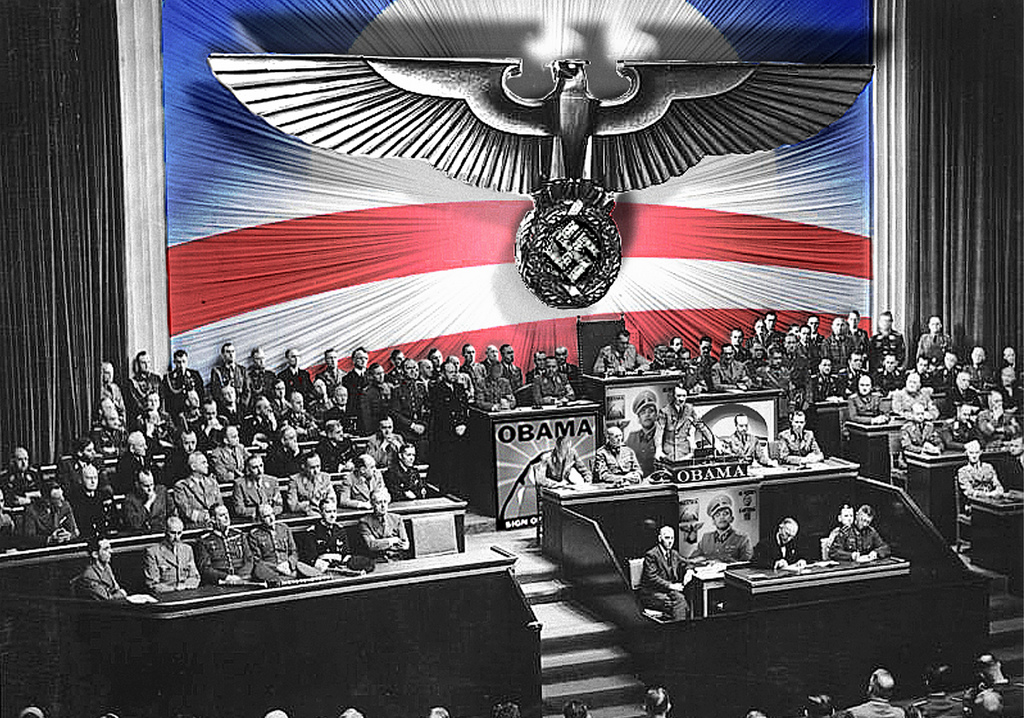
-
「空気を読む」人たちがしたこと
アウシュビッツ収容所の生き残りの人の話がTVで放映されていた。 友達は次々焼き殺されていったと
-
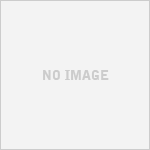
-
個人とその意見を同一視すること
なるほどのライフハックがあったのでエントリー。 個人攻撃を回避するための「我々の問題は・
-
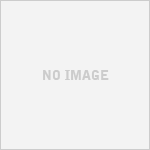
-
サスティナビリティについて
最近この言葉をよく聞くようになりました。sustain+able 持続可能性と訳されていて、続けてい
-
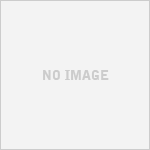
-
それでも世界はすばらしい
何度やってもだめだし、自暴自棄になってしまいそうだし、精神衛生的に悪いと思って、サーバ構築を中断、前
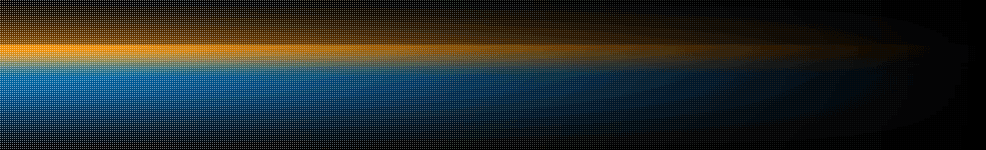






 RSS
RSS




