パーソナルとパブリック
去年くらいまで「個人の趣向や考え方は仕事に影響しない」という持論がありました。
どういうことかというと、例え人がどんな思想を持っていても、それと仕事とは関係ないということです。
例えば自分がある宗教にひどく傾倒しているとしましょう。もしそうだとしても、仕事さえきちんとこなしていれば、周りから非難を浴びるようなことは無いし、周りにも迷惑をかけないという考え方でした。
しかし1年前、あることがきっかけで個人的な価値観や振る舞いが仕事に影響を及ぼした事例を目の当たりにする出来事がありました。
そのときから「個人は個人としてあると同時に、社会の公人としても存在している」と考え方を改め始めたのです。
そして2011年の今年。
facebook元年。ソーシャルメディアはますます隆盛を見せています。
ツイッター、facebook、mixi、Google+、ブログ・・・・。
今まで知ろうとしても知ることができなかった人の考え方や行動がリーチャブルになっています。
有名企業の社長の一言や、芸能人の行動、そしてこのブログのように自分の考え方もパブリックに表明することができるようになっています。
そういう意味で言えば、facebookやtwitterなどに掲載されたらすでにパブリックなわけです。
とても分かりやすいのが「まんべくん」の事例。
自分はあの事例を、パブリックとパーソナルのパーテーションが無くなってしまった例だと認識しています。(パーソナルの中の人と、パブリックの長万部町、という意味で。)
この事例の他にも、ホテルの従業員が芸能人の目撃情報をツイートしたり、韓流批判をして炎上したり、原発批判したツイートをお気に入りにしていてそれが問題化したり、最近のソーシャルメディアのニュースは毎日のように耳にします。
佐賀県知事の「お気に入り」、話題になり削除
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110913-OYT1T00910.htm
これは、WEB自体ができて間もないメディアであり、パーソナルとパブリックの定義がされていないということが原因のように思えます。(これまではされる必要がなかった)
現代社会では、完全に自分1人で社会生活を送ることは不可能です。
ソーシャルメディアが当たり前になった今では、なおさら個人の真摯さが問われます。
それだけに社会の1人、公人(パブリック)として振舞うことが要求されるのです。
ただしそれはルールでがんじがらめにするように、制約をつけるのではなく、ある一定の基準を作ってその中で自由に運用するような、(サイトで言えばサイトポリシー)そんな意識でソーシャルメディアを楽しんで活かしていければいいんじゃないかと思います。
追伸。
久しぶりにPCでブログを書きました。やっぱりipadより全然やりやすいですね。
Google AD
- 前の記事
- プロセスが大切な訳
- 次の記事
- 慮ることと真実を明らかにすること
関連記事
-
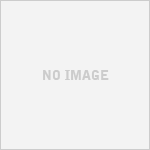
-
「企業(文化)水準が低い」とはどういうことか
企業文化(風土)について思うことがあったのでエントリー。 「貧しい」とはどういうことか - デ
-
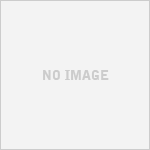
-
慮ることと真実を明らかにすること
今日ネットで見たコラムにびっくりさせられた。 大臣の失言と裏を読みたがる人々:日経ビジネスオンラ
-

-
【就活生へ】面接の1時間では人間性まで分からないよ!【持論】
桜もそろそろ見ごろを過ぎようとしていますね。 ちらほら会社のまわりで就職活動中の学生を見か
-

-
Memento Mori
卵が先か、鶏が先か、なんて議論したり思い悩んだりするのはどうでもいいこと。覚悟を決めてまずや
-
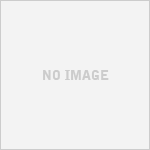
-
WordPressをインストールしたら最初にやってることまとめ
仕事でWordpress使ってるけど、とりあえずすごく役に立ちました。ありがとうございます。個人的に
-
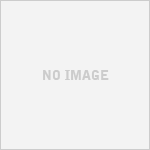
-
スティーブ・ジョブズ、CEOを辞任
http://mainichi.jp/select/world/news/20110825ddm00
-

-
サイバーカスケーディングのこれから
少し前の話。岩手県議会議員の小泉氏が自殺したと、ネットの記事を通して知りました。 <岩手県
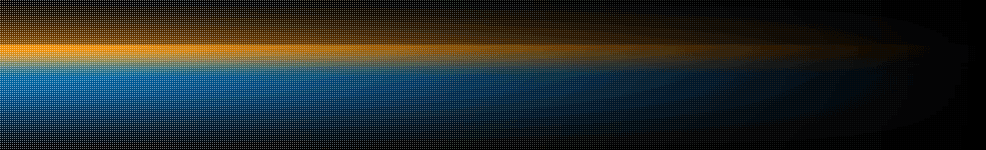







 RSS
RSS




