人は人を完全には理解できない2
公開日:
:
最終更新日:2014/06/11
イシュー, ライフハック 人は人を理解できない
さとなおさんの記事に、前回の記事にとても内容的に合っていたエントリーがありました。
人はわかりあえっこないからこそ、たまたまわかりあえたときに強い「共感」が起こる
http://www.satonao.com/archives/2012/03/post_3388.html
前回自分がポストした内容は、つまりこういうことでした。
今回はそれを踏まえて、もう少し進展させてみます。
まず一つの疑問です。
「なぜ同じ対象を感じても(見たり、聞いたり)、理解できる(共感する)ときもあれば、分かり合えないときがあるのか。」
こういう経験は誰でもあると思います。学生のころは懇意にしていて、社会人になって疎遠になり、久しぶりに会ってみたら価値観が違っていた、もしくは自分の置かれている境遇と全く異なっていて距離を感じた、ということです。また、恋愛体験において、こういうことはしばしば体験すると思います。(深くは言及しませんが。)
考えてみると、それ(共感するときもあればしないときもあるという、不一貫性)の対象は、人間だけにとどまりません。一度読んで深く共感した本でも、後で読んでみると薄っぺらく感じたり、逆に、つまらないと思っていた映画を大人になって見てみると、深く共感することがあります。
自分の場合、それは映画『ゴッドファーザー』でした。子供のころ見ても全く意味が分からなかったものが、ある程度社会が理解できてくると、言葉の意味や人物の考え方、それを取り巻く環境などに新たな発見があるのです。
ここに一つの法則が言えると思います。
対象(モノ)は同じで、感じる人間が同一であっても共感の不一貫性が起きる。
なぜなのか?
それは対象を観察する中身が変わっていること。つまり人間が成長していくということと同義です。
さきほど「感じる人間が同一であっても」と表現しましたが、厳密に言えば違います。
昨日の自分と今日の自分は違います。違う人間だから同じものを見ても違う感覚を受けるのです。
上記の事項から、もう一つ法則が言えると思います。
人間は相対的であるということ。
人は他の人との交流の中で考え、感じ、成長します。周りの人がいなければ、自分を計る価値が無くなってしまいます。それは自分の存在が無くなるということと同義ではないでしょうか。
さらに突っ込んで言うと、自分の存在を消したくないがために、人は他の人とのつながり(共感)を求め、共感をしたときには深い絆が生まれます。だから今言われているようなインターネットを使った「ソーシャルネットワーク」が人に受け入れられるのは、とても理に適っていると思うのです。
とはいえ、現実ではやはり人を完全に理解することはできません。それでも、人は他人を理解する(理解してもらおうとする)努力を止めてはいけないのかもしれません。本当に、ごくわずかな、切れてしまいそうな細い糸でもたぐって繋げていこうとして。
Google AD
- 前の記事
- 引っ越しました
- 次の記事
- facebookでログイン機能を作成してみた
関連記事
-

-
Nexus5の魅力を5つ挙げてみました
いまだにiphone4を持つ自分としては、やはり新しいスマホが欲しいわけですが、今さらiph
-
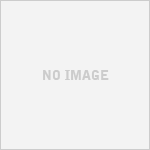
-
スティーブ・ジョブズ、CEOを辞任
http://mainichi.jp/select/world/news/20110825ddm00
-

-
自分がブログ続けていく意味を考えたよ
ブログを続ける意味を考えてみました。 1.自分用メモ 基本的に私の場合はこれがメインに来
-

-
自分の非を認める。傍観者は気にしない。
今回のプロジェクトは、結果的にはうまく行ったとは言えませんでした。個人的には「何とかなった」
-
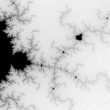
-
GoogleがDEEPMINDを買収したことと人間の未来についての感想
スマートコンタクトレンズ開発を発表したりして何かと話題のGoogleさんから、また企業を買収
-

-
ソロモン流に出演していた滝川クリステルさんを観た感想
昨日テレビ東京系で放映していた『ソロモン流』を観ました。 出演していたのは「お・も・て・な
-
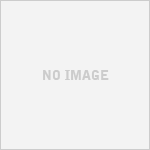
-
20年後、30年後の人が今の時代を振り返ったとき、いい時代だった、と言うだろうか。
20年後、30年後の人が今の時代を振り返ったとき、いい時代だった、と言うだろうか。 2
-
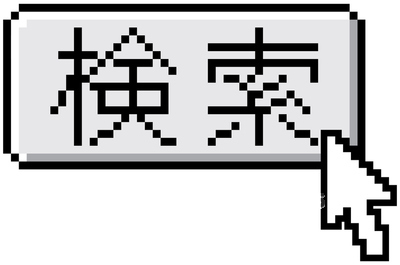
-
SEO的に去年の今とアクセス数比べてみた
今まで自分のサイトのアクセス数を気にしたことはあまりなかったんですが(オイ)、サーバ移行に伴
-

-
【感想】タモリさんが笑っていいとも!を卒業して人徳とか影響力について考えた
春は出会いと別れの季節ですね。 タモリさんが「笑っていいとも!」を卒業するという話は、
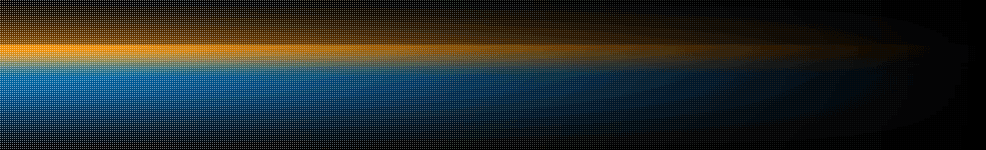







 RSS
RSS




